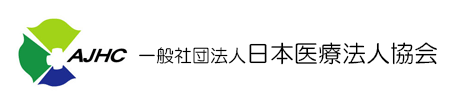日本医療法人協会ニュース 2025年4月号

■巻頭言
日本医療法人協会 会長代行/社会医療法人大雄会 理事長 伊藤伸一
■特別座談会
大坪寛子・厚生労働省健康・生活衛生局長を迎えて
健康・生活衛生政策の現状と課題
震災や健康食品被害、コロナパンデミックを乗り越え次の段階へ
地道な取り組みと検証で国民の健康を支える
大坪寛子 厚生労働省健康・生活衛生局長
加納繁照会長/鈴木邦彦副会長/太田圭洋副会長/小森直之副会長
■緊急レポート
「日本医師会・6病院団体合同声明」解説
未曾有の危機に直面 データで可視化し多方面へ訴える
太田圭洋 日本医療法人協会副会長
●NEWS DIGEST医療界の最新動向
●独立行政法人福祉医療機構貸付利率表
●編集後記
日本医療法人協会 副会長
社会医療法人大雄会 理事長
伊藤 伸一日本医療法人協会として、2025年度に解決に向け協議を進めるべき課題について提言したい。
最初は、病院経営の危機について。現在、多くの医療機関が空前の経営危機に瀕している。現状を国民と為政者に周知して期中改定を含めた緊急対応を実現しなければ、病院が消滅して地域医療が根底から崩壊する瀬戸際にあると認識してもらう必要がある。3月12日に行われた日本医師会と病院関係6団体の記者会見でも、「異常事態」と表現された現状を速やかに改善する必要がある。特に中小の医療法人病院ではコロナ対策の補助金が十分ではなく、赤字が複数年度のところが少なくない。地域医療の根幹を支えているのは中小の医療法人病院であり、蔑ろにすることは許されない。早急な働きかけと具体的解決対応に向け繰り返しの働きかけが必要だ。
次は、医療法人持分のあり方である。07年度に施行された第5次医療法改正の医療法人制度改革で「原則として医療法人は持分なし」と規定され、持分を有する医療法人の存続が不透明になった。法改正時に社会医療法人制度が創設され、その後、認定医療法人制度が創設されることで持分放棄が行いやすくなったとはいえ、法改正後18年を経ても全医療法人の約60%が「持分あり」という現実を受け止めなければならないし、再度、医療法人の非営利性と持分のあり方について幅広い協議を再開すべきと思料する。同時に、持分を有する医療法人についてはその存在の公益性を根拠として、他の中小企業と同様の相続税、贈与税の納税猶予、免除制度を設けるための協議を並行して行う必要がある。
3番目として、社会保険診療報酬・介護報酬における消費税非課税(控除対象外消費税問題)の解決があげられる。1989年に導入された消費税制度で社会保険診療報酬は非課税となり、税率10%の現在も、各医療機関の消費税負担は診療報酬の補填によって賄われてきた。しかし、それぞれの医療機関の機能が細分化・高度先鋭化することに伴い、特に大規模の急性期医療を担う病院の控除対象外消費税負担が著しく増大し、病院の運営に大きな影響を及ぼす事態となってきた。 診療報酬の補填状況についても、個々の医療機関の実態は一切考慮されず、同一医療機能の集団全体で平均的に補填されているのが現状だ。 同一の医療機能集団のなかでも、病床規模や設備投資の多寡によって損税が発生することは避けられないことは明らかで、その実態を検証するために補填のばらつきを明らかにするよう求めているが、全く対応されてこなかった。
病院団体の対応として、まずは個々の病院の補填のばらつきを明確にして診療報酬での補填の限界を示し、抜本的解決のために消費税課税化に向けてさらなる活動を推進する計画である。
■特別座談会 大坪寛子・厚生労働省健康・生活衛生局長を迎えて
健康・生活衛生政策の現状と課題
震災や健康食品被害、コロナパンデミックを乗り越え次の段階へ 地道な取り組みと検証で国民の健康を支える
高齢化の進展とともに、健康・生活衛生の重要性はますます高くなっている。 そうしたなかで、健康・生活衛生関連の政策は現在どのような方針のもとで展開されているのか。 現在は健康・生活衛生局長として陣頭指揮をとる大坪寛子局長を迎え、コロナ禍を経て、生活環境の衛生状態維持・向上が国民レベルでも認識されるようになった。 今回、医系技官として数々の医療政策にかかわる一方、健康・生活衛生分野行政にも精通し、 現在の健康・生活衛生行政の方向性や現状、課題などについてうかがった。
(以下、掲載省略)
~ご意見・ご感想をお寄せください~
より良い誌面づくりのためにも、会員をはじめ読者の皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。宛先は事務局までお願いします。 (Eメール:headoffice@ajhc.or.jp)